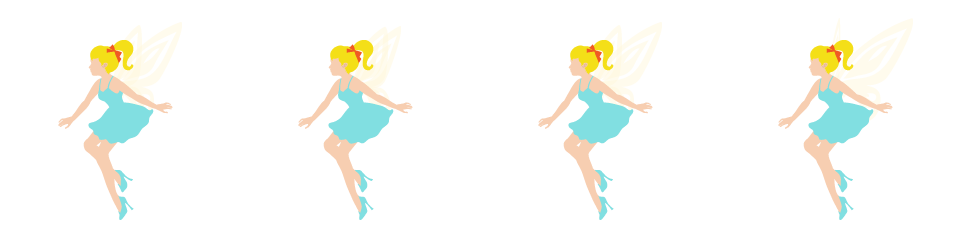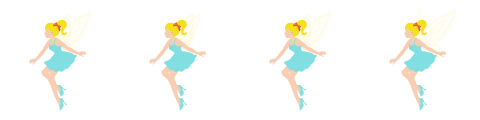
司法書士はよく「街の法律家」と言われます。
この言葉のとおり、当事務所には、いろいろな方が、ご依頼やご相談に来られます。
その方々が、少しでも早く、解決方法を見つけられるよう、お手伝いをさせていただき、
また幸せな生活に戻っていただけたらいいなと思っております。
「清く正しく美しく」をモットーに、日々研鑽しております。
株式会社をはじめとする各種会社及びその他の法人の設立、役員変更、本店移転、増資、等多彩な分野に精通しており、また、近時の改正商法にもいち早く対応しています。登記申請のみならず、定款・議事録等の書類の作成や、契約書のチェックも綿密に処理します。
売買・相続等による所有権移転、担保の設定・抹消等の一般的な案件から、金融機関より受託する多量案件まで、幅広く業務を行っています。
訴額が140万円以下の民事事件に関する訴訟手続(上訴・再審提起 ・強制執行を除く)和解手続、支払督促手続、調停手続等を代理します。売買代金(売掛債権等)・請求事件・敷金返還請求事件・不法行為(交通事故による物損等)に基づく損害賠償請求事件等について、迅速な処理を心がけており、事件を長期化させることのないよう、裁判外での和解手続を第一に考えています。
高齢者の方々が直面する様々な問題(資産管理・相談等)について、総合的にサポートします。親類縁者に知られたくないようなケースでも、秘密の保持に細心の注意を払いながら粛々と業務を行いますので安心です。さらに、高齢のため自己の判断能力が不十分になった際には、任意後見契約を締結することで、ご本人の財産管理、身上監護の事務の全般または一部についての処理を行うことができます。また、後見登記申請の手続きや遺言書作成、遺言執行についてのご相談も承ります。
多重債務をかかえてお困りの時に、自己破産・任意整理・特定調停、民事再生手続等のご相談を承ります。それぞれの事例に応じた返済プランを構築します。
平成2年熊本生まれの熊本育ちです。
済々黌高等学校、熊本大学法学部卒業後、縁あって当事務所に勤務することになりました。5年間司法書士補助者として勤務し、平成30年度の司法書士試験に合格後、すぐに司法書士登録致しました。
登録後も、おかげ様で毎日のように相談をいただき、様々な事務に携わることができております。
不動産決済業務のみならず、これからますます増えるであろう相続手続や近年拡がりつつある事業承継、信託、財産管理業務についても常に情報収集に努めます。
依頼者の方々が安心して本業に専念できるよう、また、安心して問題が解決するよう“速く、正確に”司法書士執務に取り組んで参ります。どんな些細なことでも、身近な法律相談の窓口としてご相談いただければ幸いです。
はじめまして。橋本と申します。
こちらの事務所には良いご縁をいただきまして、平成28年からお世話になっております。
司法書士業務や法律的な分野に関しては直接携わることは少ないのですが、私は主に職員全員の経理と総務を担当させて頂いております。
決して堅苦しい事務所ではございませんので、何かご相談事がございましたら、気軽にお立ち寄り下さい。
美味しいコーヒーを入れてお待ちしております。
丁寧な対応を常に心がけ日々の業務に取り組んでおります。お客様のご負担がなるべく少なくなるよう、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
2022年9月から補助者として勤務しております。明るくコミュニケーションをとることを心がけています。どうぞよろしくお願いいたします。
福岡県から大学進学で熊本に移り住み、縁あって当事務所に補助者として勤務しております。皆様のお役に立てるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。